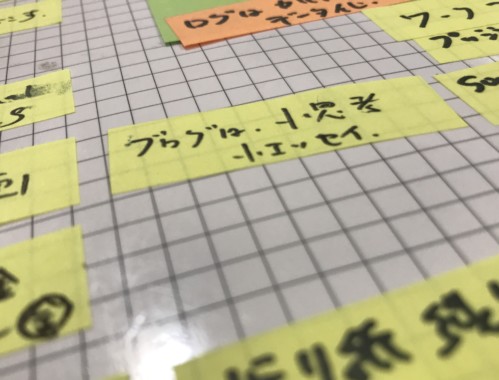あなたの声を聴く人は。@声を演じる④
引き続き、映画「英国王のスピーチ」について。
→「エエ声」が、欲しいのだ!@声を演じる①
→「声」は快をつくるのか?@声を演じる②
→歌えば分かる。@声を演じる③
映画の中では、押し込められていた怒りと抑圧された心を解放する時、ジョージ6世は吃音を忘れるのです。
心の奥にある痛みや怒り、悲しみがあらわになる時、彼が「生まれつき」のものと固く信じ込んでいた吃りさえも引っ込んで、彼は突然「声」と「言葉」を獲得する。
「声」と「言葉」がよどみなくあふれた時、自然に「歌」が生まれる。
声が震えていても、節まわしがどんなにつたなくても、彼は確かに「歌って」いたのでした。
その光景は、まるで一つの泉が湧き出したのを目の前にしているかのような驚きを感じさせます。

バッキンガム宮殿からの眺めですね。
そもそも「歌の源泉」には、なにがあるのでしょうか?
「声」と「言葉」をあふれさせる、自分自身の生身の感情と記憶、願い、欲望、追憶。
歌ってみれば、自分の心の在り処と、その色が見える。
ためらいや羞恥心を隠れみのにしながらも、「声」と「言葉」の中に自分自身の内側が限りなく映し出されているのが分かる。
かつて私が恩師に「歌って」と繰り返された時に感じた激しい羞恥心と反発は、「歌う」という行為が自分の内側をあらわにしてしまうということだと、わたし自身が本能的にわかっていて、当時はそれを受け入れられなかったゆえだと今は思います。
あの時の私には、明らかに二つの信頼が欠けていました(今も時折無くしかけますが)。
この二つについては、ローグの述懐の中にそのヒントが見つかります。
When the Great War came, all our soldiers were returning to Australia from the front, a lot of them shell-shocked, unable to speak.
Somebody said, Lionel, “You’re very good at this speech stuff.
Do you think you could possibly help these poor buggers?”
I did muscle therapy, exercises, relaxation, but I knew I had to go deeper.
Those poor young blokes had cried out in fear.
No one was listening to them.
My job was to give them faith in their own voice, and let them know that a friend was listening.
第一次世界大戦が起こり、前線から兵士たちがオーストラリアに戻ってきた時、彼らの多くが戦争神経症で言葉を失っていた。
誰かが自分に言ったんだ、‘ライオネル、喋りにかけては君は得意だ。可哀想な彼らを君ならどうにか助けられるのではないか?’ と。
筋肉の運動、鍛錬や療法もやったが、私は問題がそこに止まるものではないとわかっていた。
可哀想な彼らは恐怖の中で声もなく叫んでいたのに、誰一人耳を傾けようとしない。
私の仕事は彼らに自分自身の声への信頼を取り戻すこと、そして彼らに「君の友人が、君の言葉に耳を傾けているんだよ」と知らせることだった。
信頼の一つは自分の声と言葉への信頼。
ごまかすこともサバをよむことも、偽ることもできない、だからこそ信じるに足るものだ、という確信。
二つ目は、自分の声に耳を傾けてくれる人への信頼。
コンサート会場のシンとした客席も。
はじめましての、一見さんも。
自分の目の前にいる人々が、自分の声を待つ友人なのだ、という信頼。
自己の内側と外側(他者)に向けて太い矢印を描き、確かな信頼を育てたとき、ようやく力強い「歌」が生まれるのかもしれない、と今は考えています。